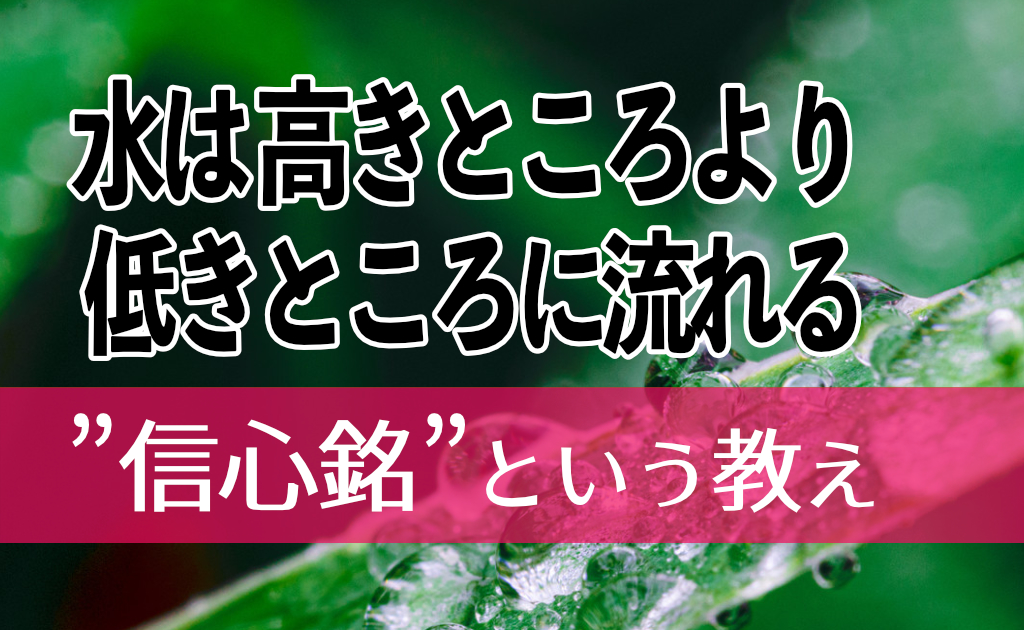
六官の対象に逆らわなければ、元々ブッダの悟りと変わりないのだ。智者はことさら何もしない、愚者は自分の縄で自分を縛っている。存在はおよそ変わったものなぞないのに、人は訳もなくっつきたがる。自分の心で自分を使うことは、とんでもない間違いではないのか。
六塵悪(にく)まざれば、還(ま)た正覚に同じ
智者は無為なり、愚人は自縛す
法に異法無し、妄(みだ)りに自から愛著す
心を将(も)って心を用(もち)う、豈(あ)に大錯(たいしゃく)に非ざらんや
六官の対象に逆らわなければ、元々ブッダの悟りと変わりないのだ。智者はことさら何もしない、愚者は自分の縄で自分を縛っている。存在はおよそ変わったものなぞないのに、人は訳もなくっつきたがる。自分の心で自分を使うことは、とんでもない間違いではないのか。
『禅語録16 信心銘 梶谷宗忍』
外の世界の対象にのまれてはならない
六塵悪まざれば、還た正覚に同じ
智者は無為なり、愚人は自縛す
『六塵悪まざれば、還た正覚に同じ』の「六塵」とは前回お話したとおり、六境のことで、私たちの外にある6つの対象のことです。その6つの対象を嫌がらなければ、それはそのまま正覚、悟り、本来と同じだというのです。「悪まざれば」とは、素直になれば、とらわれなければという意味なのです。眼を開き、耳をそばだて、外の世界を素直に、とらわれずに見開きなさい、それは悟りと同じ事である。
『智者は無為なり、愚人は自縛す』の「無為」とは正覚と同じ意味です。悟り、本来の事です。『いろは歌』に
色はにおへえど 散ちりぬるを 我が世たれぞ 常ならむ 有為の奥山 今日越こえて 浅あさき夢見じ 酔ひよいもせず
とありますが、「有為の奥山 今日越こえて」の有為とは、無為、悟り、本来の反対の意味で、迷いのことです。『老子』に「聖人は無為にして化す」とか、「無為にして而(しか)も為(な)さざるは無し」とありますが、聖人とは為して為したとも思わない。
バスや電車で、お年寄りに席をゆずって、ゆずったとも思わない。道ばたでゴミを拾って、拾ったとも思わない。そのままが本来のところ。そういう者を聖人とか、智者というのです。
ところが愚人は、「ありのまま」ということがわからないので、ゴミを拾った方がいいかな、席をゆずったぞと他人の視線、評価を気にしてしまう。それは私たちの外にある6つの対象、六塵、六境からの視点で見てしまうと言うことです。己の視点では無く、外の視点で見てしまうのです。それは自縄自縛で、本来のところではありませんね。
心が空になり、何も思わなくなるならば、外にある全世界は悉くみんな自分になる。悟りを開くといいます。「開く」。開く、何を開くのですか、六境を気にしてしまう殻を開き、吾の心を解放してあげると言うことです。「吾の心」=「悟」です。
山川草木悉皆成仏、森羅万象、ことごとく吾である。本当の境地とは六境を気にしてしまう殻を開き、吾の心を解放している境地のことです。その状態を「本来」というのです。「本来」の境地にいるときならば、頭の中で考える必要も無く、立っているその場が「道」の上です。だから「唯嫌揀択」、二元対立という考えを起こすなと言うのです。もう少し言いますと、畢竟、二元対立とは内と外の視点の対立とも言えます。
法に異法無し、妄りに自から愛著す
『法に異法無し、妄りに自から愛著す』の「法」ですが、これは近代的意味の法律や規則、ルールという意味ではありません。あらゆるもの道理という意味です。
「法」という字をご覧下さい。水に関係する「氵」に「去る」と書きますよね。面白いと思いませんか。水が流れるという言う意味です。水は高いところから低いところに流れ去る。これはあたりまえのことです。もともと「法」とは、水が流れるが如く、水が流れるというのは、森羅万象、誰もが不思議に思わない、しごくあたりまえのことと私は解釈しています。「諸法無我」。我なんぞない。これは水が低き流れるが如く、春になったら花が咲くが如く、至極あたりまえのこと。
梅の花は白くて五弁です。桜の花も同じく五弁。ですが、桜色をして花びらが花びらには切れ目がある。スイセンの花は白くて筒状になって六弁です。それぞれの花がちゃんと決まりがあります。水が低きに流れる決まりと一緒です。「三日見ぬ間の桜かな」。昨日咲いたかと思ったら、今日にはもう散ってしまう。毎日、毎日、刻々と動いている。水が低きに流れる決まりと一緒です。それが「法」というものです。
私たちはそれぞれ持って生まれた六根(感覚器官)によって、梅の花が好きな人、スイセンの花が好きな人、そこ(六境)に好き嫌い(六識)が生じ、執着してしまいます。しかし梅の花もスイセンの花もみな花であることには変わりありません。
『金剛経』の有名な一文に「是の法は平等にして高下有ること無し」とあります。富士山は高く、船岡山は低い。信濃川は長く、鴨川は短い。白鳥は白く、カラスは黒い。それが「法」というものです。それを平等と仏教は言います。
実は私たちも、背の高い人もいれば、低い人もおり、痩せた人もいれば、太った人もいる。男もおれば、女もおり、若い者も年寄りもいる。日本人もおれば、外国人もいて、賢い者おれば、そうでないもの。運動のできる者おれば、そうでないものもいます。でもそのことが「法」なのです。「是の法は平等にして高下有ること無し」なのです。
心を将って心を用う、豈に大錯に非ざらんや
その水が低きに流れることを受け止めないで、水はこう流れるはずだ、水をこう流したいなどと思うことは、本来ではありませんよね。悟りを得ようとか、煩悩を滅尽しようとか考え続け、そのことにとらわれてしまっては、道を歩もうとすることも、やっぱり本来ではありません。それが『心を将て心を用う』という意味です。
「自分探し」と言われて久しい世の中です。この自分探しですが、自分を探しているそれが自分なのに、自分探すこと自体が六塵(=六境)、つまり自分の外にある対象物になっている。自分が自分で無くなってしまう。それが『豈に大錯に非ざらんや』です。